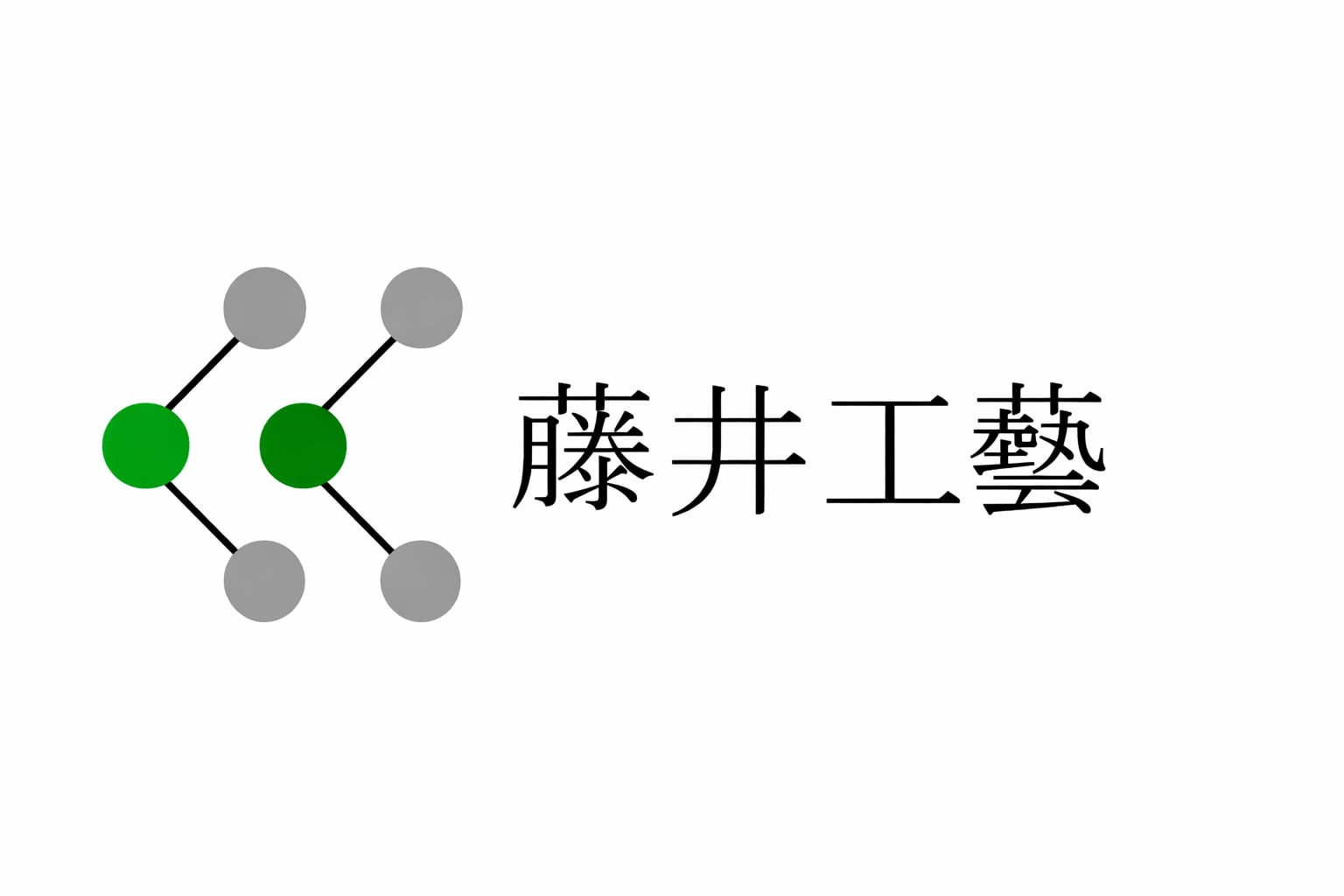2025/07/18 08:47

近年、自動車の電子化が進んだことで、電子パーツを自作して車に取り付けるユーザーが増えています。LEDテープのみならずセンシング機材を自作取り付けしている事例も珍しくありません。本記事では、車に電子パーツを自作して取り付ける際に絶対に押さえておくべき注意点を、電気設計・EMC(電磁両立性)・耐久性の観点から総合的に解説します。
1. 車載電源(12V)の特性を理解する
車は通常直流12Vの電源を使っていますが、実際の運用電圧は13〜14.4V程度とやや高く、電圧変動も激しいのが特徴です。特にエンジンスタート時のクランキング中は9V以下に落ち込むこともあり、そういった変動に対応した設計が求められます。
具体的な注意点:
• 電源入力には過電圧・逆電圧防止のためのダイオードやTVS(トランスジェントボルテージサプレッサ)を入れる
• 電源回路には三端子レギュレータやスイッチング電源を使い、安定供給を意識する
• 必ずヒューズを使用し、過電流からシステムと車両を守る
電源設計が甘いと、不安定動作や誤動作だけでなく、車両の他の電子機器への干渉や発煙・発火の原因になります。特にノイズフィルタやデカップリングコンデンサを入れない回路は、長期的に誤動作を起こす傾向があり、最悪の場合、運転中に動作停止するリスクもあります。
2. EMC(電磁両立性)と電波干渉への配慮
車は走行中、さまざまな電磁ノイズ環境にさらされます。加えて、自作回路が発する電波ノイズが、車載ナビ・無線・レーダー・スマートキーなどに干渉すると、安全上重大な問題を引き起こします。
EMC対策のポイント:
• シールドケーブルやツイストペア線を用い、信号線からの放射を抑える
• 電源ラインにLCフィルタやフェライトコアを挿入し、スパイクノイズを抑制
• 高速スイッチングを伴うマイコンやドライバIC周辺にはグランドプレーンを確保し、基板設計から対策
• ケースや筐体に導電性素材を用いることで、ノイズの漏洩を防止
特に安価なスイッチング電源やチャージポンプICは、EMC対策が甘い場合が多く、ラジオにノイズが乗る、スマートキーの反応が悪くなるなどの症状が発生する可能性があります。これらは自作の「見えにくい落とし穴」とも言えます。
3. CAN通信・OBD2への接続のリスク
車両の多くのセンサー情報は、OBD2またはCAN通信から取得できますが、これは非常に繊細なバス通信です。誤った接続や、負荷の大きいデバイスを接続すると、通信が妨害され、警告灯の点灯や制御系の不具合を招く恐れがあります。
注意すべきポイント:
• OBD2やCANは読み取り専用で使うのが原則
• 配線には**終端抵抗(120Ω)**の存在やバスのインピーダンスを考慮
安全な範囲でデータを扱いたい場合は、市販のOBD2インターフェース(ELM327系など)を介してBluetooth経由で取得するのが安全です。
4. 防水・耐熱・耐振動の設計をする
自動車の使用環境は家庭用電子機器とは比較にならないほど過酷です。気温は夏場に60℃を超え、走行中は常に振動、場所によっては水やオイルにもさらされます。
実用的な対策:
• 基板はシリコンコーティングやホットボンド固定で絶縁と防振対策を
• コネクタは脱落防止のロック付きタイプを使用
5. アース処理の正しい知識
車のGNDはシャーシ全体に接続されていますが、どこにでもつなげば良いというものではありません。
アースの基本ルール:
• 複数の機器で共通GNDを取るとノイズのループが起きるので避ける
• オーディオや高精度センサー系はアナログGNDとデジタルGNDを分離する設計も検討
ノイズによる誤動作や、GND浮きによる信号エラーは、自作回路で非常によく起こるトラブルです。特にアース不良は再現性が低く、原因特定が困難なので、最初から丁寧に処理しておくことが重要です。
まとめ
車両に電子パーツを自作して取り付ける作業は、技術的な達成感も大きく、非常に楽しいものです。しかしその反面、誤った知識や軽率な設計によって重大事故につながるリスクもはらんでいます。
特に、**電源設計とEMC(電磁適合性)**を軽視すると、車両の他の機器に悪影響を及ぼすだけでなく、運転中に体調不良を引き起こすほどのノイズを発する例もあります。動悸や頭痛の原因が、実は自作パーツのノイズだったという報告もあります。
安全に、楽しく、そして確実に電子DIYを車に活かすために、基礎から一つ一つ丁寧に設計していきましょう