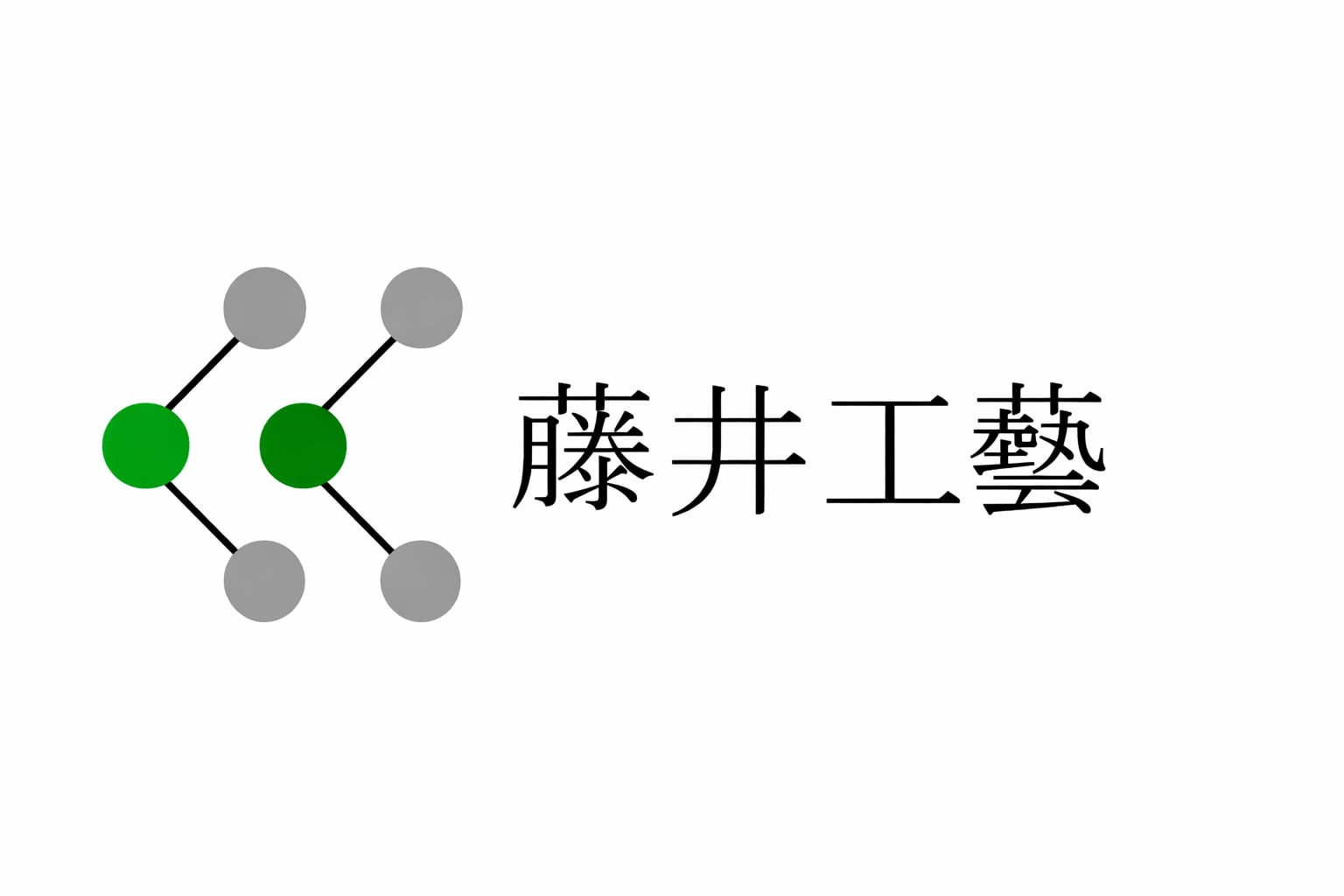2025/07/04 08:33

ものづくりに熱中した結果、見えなくなったもの
私は昔から、「良いものを作る」ことに情熱を注いできました。
特に技術を磨くこと、誰もやっていないことにチャレンジすることに強い喜びを感じます。
世の中にまだないものを形にする。
他にはない高性能、高品質を目指す。
その姿勢は自分の強みでもあると思っています。
しかし、そんな私が作ったものは、いつも必ず売れるわけではありませんでした。
⸻
シーズ目線とニーズ目線の違い
ここで改めて整理します。
• シーズ目線:自分の技術や強みを起点にする考え方
• ニーズ目線:お客さんの困りごとや欲求を起点にする考え方
【具体例】
■ シーズ目線の商品
→ 最新技術を詰め込んだ、機能盛りだくさんのスマホアプリ。
でも、操作が複雑すぎて使いこなせない人が続出。
■ ニーズ目線の商品
→ 必要最低限の機能だけに絞ったシンプルな家計簿アプリ。
「これなら続けられる!」と利用者が増え、口コミで広がる。
⸻
なぜシーズ目線はうまくいかないことがあるのか?
シーズ目線で作ると、どうしても自分の理想を押し付ける形になりがちです。
• 高性能だけど高すぎる
• 多機能だけど難しすぎる
• 独自すぎて理解されない
たとえば、ある家電メーカーは、
「全自動で部屋中を掃除してくれるロボット掃除機」を開発しました。
技術は素晴らしいものでしたが、価格は30万円超。
さらに設置や設定が面倒で、一般家庭ではなかなか普及しませんでした。
一方、後発メーカーが「ワンボタンでスタートできる」「5万円で買える」ロボット掃除機を出すと、爆発的にヒット。
「使う人の視点」があるかないかで、結果はまったく違うのです。
⸻
ニーズ目線で考えると、世界が変わる
私はこの経験から、自分のスタイルを見直しました。
まずは「作りたいもの」ではなく、「求められているもの」から考える。
技術はそれを支えるために使う。
たとえば、あるとき「持ち運びに便利な小型バッテリーが欲しい」というニーズに気づき、
超大容量ではなく、軽くて薄いバッテリーを設計しました。
技術的には、もっとすごい大容量バッテリーも作れました。
でも、あえて「ニーズに合った機能だけ」に絞ったことで、初めて「これ欲しかった!」という声をもらうことができたのです。
⸻
シーズもニーズも、どちらも欠かせない
ここで気づいたのは、
**「ニーズに応える形でシーズを活かす」**という考え方の大切さです。
つまり、
• ただのニーズ追いではなく
• ただの自己満足のシーズでもなく
「自分にしかできないこと」を「必要としてくれる人」に届ける。
このバランスこそが、事業成功の鍵だと思うようになりました。
おわりに
ぜひ一度、相手の立場で考えてみてほしいです。
• 本当にその性能が求められているのか?
• 本当にその機能は使いやすいのか?
• 本当にその価格は適正なのか?
あなたの持っている技術や情熱は、必ず誰かの役に立てます。
ただ、それをどう届けるかを考えるだけで、結果は大きく変わると私は信じています。