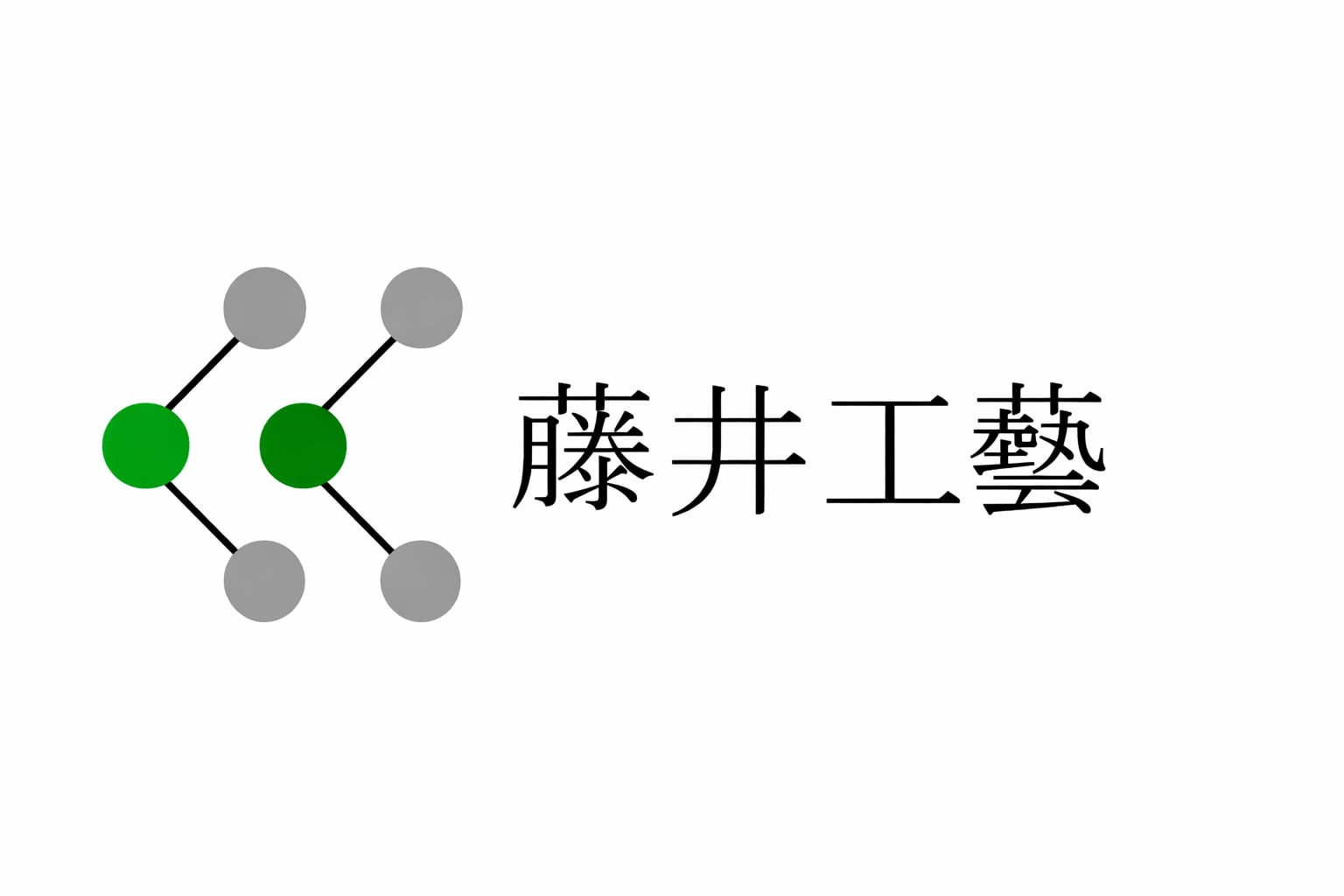2025/03/31 19:45

アート思考とデザイン思考の違い
製品を作るとき、多くの企業は「どうすれば売れるか?」を考えます。
そのときに役立つのが「デザイン思考」です。デザイン思考は、ユーザーのニーズを深掘りし、問題を解決するための手法です。簡単に言えば、「求められているものを、よりよく作る」アプローチです。
一方、「アート思考」は真逆のアプローチを取ります。アート思考の中心にあるのは「自分が何を表現したいか?」です。ユーザーの意見や市場のトレンドに左右されず、自分の内側から湧き出るものを形にしていくのが特徴です。これは「万人受けしなくても、自分のスタイルを貫く」姿勢とも言えます。
私たちの企業の製品は、まさにこの「アート思考」に基づいています。だからこそ、万人受けするものではありません。しかし、それが大きな強みでもあるのです。
尖ることの意味 〜アート思考の本質〜
アート思考の根底にあるのは、「自分の美学を貫くこと」です。
一般的なビジネスでは、「市場のニーズを満たすこと」が重要視されますが、アート思考では「自分が納得できるものを作ること」が最優先されます。
このアプローチは、時には孤独を伴います。周りから「売れない」「流行らない」と言われることもあるでしょう。
しかし、本当にユニークで価値のあるものは、最初は理解されないものです。
Appleのスティーブ・ジョブズは
最初は異端視されたクリエイターが、後に世界を変えた例は数えきれません。
「市場が求めるもの」ではなく「自分が作りたいもの」を追求し続けました。
そして、結果的に「それが欲しい」と思う人々に届き、強烈なブランドを確立しました。
私たちも、同じ姿勢で製品を作っています。
だからこそ、「万人に受け入れられなくて当然」なのです。
尖り続けることで、いつか刺さる
「万人受けしない」というのは、言い換えれば「特定の人には強烈に刺さる」ということです。
マーケティングの世界では、「誰にでも売れる商品」は「誰にも刺さらない商品」になりがちです。
尖った製品は、市場の中でニッチなポジションを確立できます。
ニッチだからこそ、熱狂的なファンが生まれるのです。
例えば、
• ランボルギーニは、大衆向けの車を作らず、走りにこだわる車を作り続けることでファンを獲得しました。
ブランドの共通点は、「最初から大衆向けを狙わなかったこと」です。
ターゲットを狭く絞り、独自のスタイルを貫くことで、熱狂的なファンがつきました。
私たちの製品も、まさにその方向性です。
「売れるもの」ではなく、「本当に価値があるもの」を作る。
結果的に、それが必要な人に届く。
続けることが最大の戦略
「でも、尖り続けて売れなかったらどうするのか?」
この疑問は、多くの人が抱くでしょう。
答えはシンプルです。**「続けること」**です。
どんなに素晴らしいアイデアでも、一瞬で広まることはありません。
時間をかけて認知され、じわじわと理解され、ファンがついていくのです。
村上春樹の小説が、最初は日本よりも海外で評価されたように、
本当に価値があるものは、理解されるのに時間がかかります。
だからこそ、諦めずに続けることが重要です。
アート思考の本質は、「売れるために作る」のではなく、「作りたいから作る」こと。
その姿勢を貫き続けることで、いつの日か「これは唯一無二だ」と思ってくれる顧客に出会えます。
最後に:尖り続ける覚悟
「尖る」ということは、「妥協しない」ということです。
私たちは、トレンドに流されず、
市場に迎合せず、
ただひたすらに「作りたいもの」を作ります。
それが、いつの日か本当に価値を理解してくれる人に届くことを信じて。
「万人に受けなくてもいい。
ただ、必要な人には絶対に刺さるものを作る。」
この信念のもと、これからも尖り続けます。